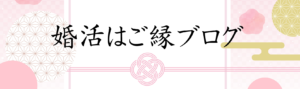結婚において、「上昇婚」 という言葉を耳にすることがあります。これは、「女性が自分よりも経済的・社会的に地位の高い男性を結婚相手に選ぶ傾向」 を指します。実際、多くの女性が結婚相手に対して、「自分よりも収入が高い」「社会的地位が安定している」「学歴が高い」 といった条件を求める傾向があると言われています。
では、なぜ女性は上昇婚の人が多いのか? その理由を、社会的背景や心理的要因を交えながら詳しく解説していきます。
目次
1. 上昇婚とは?
「上昇婚(ハイパガミー)」 とは、結婚において女性が自分よりも経済力・学歴・社会的地位の高い男性を選ぶ傾向を指す言葉です。 これは世界的に見られる現象であり、日本に限らず、多くの国や文化で共通する傾向があります。
例えば、「女性は男性に年収の高さを求めるが、男性は女性にそれほど高い収入を求めない」 というデータが示すように、結婚市場において「女性は経済的に安定した男性を求める傾向が強い」 ことがわかります。
2. 女性に上昇婚が多い理由
① 本能的な生存戦略としての「経済的安定」
進化心理学の観点から見ると、女性は本能的に「安定した生活を送れる相手」を求める傾向がある とされています。
- 女性は妊娠・出産の負担があるため、経済的に安定したパートナーを選ぶことで安心感を得る。
- 歴史的に見ても、男性の社会的地位や経済力が高いほど、家庭が安定しやすかった。
特に、結婚を「家庭を築くこと」と考えた場合、「収入が高く、安定した職業に就いている男性」と結婚することは、将来のリスクを軽減する選択肢となります。
② 社会構造の影響
現代では、女性の社会進出が進んでいるものの、収入面では男女格差が残る傾向があります。 そのため、多くの女性が結婚において「より高収入の男性を選ぶことで、生活水準を向上させようとする」 のは自然な流れと言えます。
- 男女の賃金格差が存在するため、経済的安定を求める女性が多い。
- 伝統的な価値観の影響で、「男性が家計を支える」という考えが残っている。
例えば、日本のデータでは、同じ職業でも男性の方が平均年収が高いケースが多い ため、結婚相手に対して「自分より収入が高い男性」を求める傾向が続いています。
③ 結婚市場における選択肢の違い
婚活市場において、男性と女性では結婚相手を選ぶ基準が異なります。
- 女性は「経済力」「安定性」を重視する傾向がある。
- 男性は「外見」「年齢」「家庭的な要素」を重視する傾向がある。
この違いにより、女性は自然と「上昇婚」を目指しやすくなる のです。
④ 社会的ステータスの向上を求める心理
結婚は単なる恋愛の延長ではなく、社会的なステータスの向上にもつながると考えられています。
- 「高学歴・高収入の男性と結婚することで、自分の社会的地位も上がる」 という考え方。
- 結婚によって「より良い環境に身を置ける」という期待感。
特に、親世代の影響や、周囲の価値観によって「良い結婚=上昇婚」という認識が強まることもある ため、女性が上昇婚を目指す傾向が続いていると考えられます。
⑤ 本人の努力と向上心の影響
もちろん、すべての女性が上昇婚を求めるわけではありませんが、「より良い生活を送りたい」「尊敬できる相手と結婚したい」という向上心がある人ほど、上昇婚を意識しやすい 傾向にあります。
- 「自分と同じレベル以上の人と結婚したい」と考える女性が多い。
- 「結婚によって成長できる相手を選びたい」という価値観を持つ人もいる。
つまり、上昇婚を求める背景には「より良い人生を送りたい」という前向きな気持ちがあることも確かです。
3. 上昇婚の傾向は変化している?
近年、女性の社会進出が進むにつれて、「上昇婚」ではなく「対等な関係」を重視する女性も増えてきています。
- 「共働きが当たり前」の時代になり、女性も経済的に自立できるようになった。
- 「収入だけでなく、価値観や相性を重視する結婚」が増えている。
- 「家事や育児を平等に分担できる男性」を求める女性も増えている。
そのため、従来の「男性の方が高収入でなければならない」という価値観は少しずつ変化してきている のが現状です。
4. まとめ:なぜ女性は上昇婚の人が多いのか?
女性に上昇婚が多い理由は、以下のような要因が影響しています。
- 本能的な生存戦略として、経済的安定を求める傾向がある。
- 社会構造の影響で、収入や地位が高い男性を選びやすい。
- 結婚市場における男女の価値観の違い。
- 結婚を通じて社会的ステータスを向上させたいという心理がある。
- 向上心のある女性ほど、尊敬できる相手を求める傾向がある。
しかし、近年では「上昇婚」にこだわらず、対等な関係を求める女性も増えており、結婚の価値観は変化しつつあります。 今後は、収入や社会的地位だけでなく、「お互いを支え合える関係」や「価値観の一致」が重視される時代になっていくでしょう。